L’insoutenable légèreté de l’être (by Milan Kundera: 1984) [読書’13]
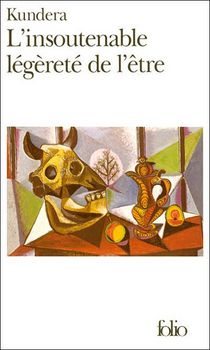
夏休み中、風邪をひいて一日ベッドで過ごした時に読んだクンデラの「La valse aux adieux(別れのワルツ)」が印象に残っていたので、ホストファミリーの家にあった別の彼の作品も読んでみることにしました。それが「存在の耐えられない軽さ」です。
最初タイトルを見た時は、「何だこれ?」という感じでした。読み終わった今でも、「一体どういうことを言いたいのだろう」とよく分からないままです。そしてフランス語圏では、この本がヒットしてクンデラの名前が知られるようになったそうです。なぜこの本で、と、ホストファミリーにも理由を聞いてみましたが、「よく分からない」という答えが返ってきました。
この本、一応小説ですが、たまにクンデラの哲学/考え方が割り込んでくる、哲学書でもあります。三人称で話が進んでいたと思ったら、いきなり一人称で始まる章があって、最初はよく混乱しました。というか、最後まで戸惑うことが多い小説でした。「キッチュ」とは何か、とかなり哲学的な話が入ってきて、慣れていないと相当混乱します。哲学の国であるフランス語圏、こういった本を好む人が多かったのかな、と個人的には思いました。
そして、このクンデラの哲学考察が入るだけでなく、話の進め方も込み入っていました。時系列で話が進むのではなく、各出来事をバラバラにして、話が進んでいます。本来の小説で「結末」に当たるであろう部分が本の真ん中に来ていて、「後100ページ近くもあるのに?」と思ってしまいました。本の最後はトマ(登場人物)が部屋に上がってきて、電気をつける、というシーンで終わっています。結末をここで明かしても、全くネタバレにならないというかなり変わった小説のような気がします。もちろん、時系列通り話が進まない小説もあると思います。が、そういった作品でも一応最終章を読めば一応話が解決、となっています。その「解決」の部分がこの本には無いため、最後まで読んでも読み終わったという感じがしませんでした。
この消化不良、の感じも人生に似ているのかな、と思いました。悲劇(それが死という形であっても)が起きても、周りに居る人たちはそこで人生が終わるわけではないし、なんだかんだ続いていきます。こういった人生の大きな出来事が区切りとなっているかに見えても、実際長い目で見てみると、大した区切りではなかったり、また小さな出来事が大きな転換になるということもあります。この小説の「バラバラになった話」は、必ずしも起承転結通りに人生が進まないという意味で、人生っぽいのかな、と個人的に思いました。人生を語るのが好きなフランス語圏の人たちがこの小説を好むのは、その複雑さのせいなのでしょうか。
夏の読書 最終回 [読書’13]
先日から新学期が始まり、夏の読書も最終回となりました。本は読み続けますが、この企画夏休みに読んだ本、というテーマで始めたので区切りをつけておこうと思います。そこで、夏休み中に読んだ16冊から自分のベスト3を作ってみました。3冊選ぶのに苦労したので、3冊内の順位はありません。
1. ”Les Derniers Jours de Nos Pères” by Joël Dicker
フランスで大きな賞をもらった「La vérité sur L’Affaire Harry Quebert」を最初に読み、とても興味を持ちました。この小説がとても気に入り、これを超えるのは難しいだろうと勝手に思い込んでいました。今のところ、この著者の出版作品は2冊だけですが、個人的には最初に書かれた”Les Derniers Jours de Nos Pères”の方が気に入っています。第二次世界大戦中、と時代、そしてテーマ自体も重く決して笑えるような話ではありません。が、「究極の選択」というテーマが作品中何度も出てきて、色々考えさせられます。自分ならこの状況で何を犠牲にして、どちらを選ぶのかということを読みながら、何度も考えました。次回どんな作品を書いてくれるのか、今からワクワクしています。次回作が存在するかどうかさえもまだ分かりませんが、この2作品で終わらないことを大きく期待しています。
2. ”Saga” by Tonio Benacquista
彼の作品はいくつか読みましたが、この「Saga」がずば抜けて面白いと思います。あり得ない結末だけれど、テレビ業界を面白く(皮肉を込めて)描いていました。笑えるシーンでも「よく考えてみたら、結構深刻なことかも」と思わされてしまいました。
最近では、色々な小説が映画化されています。が、これは脚本家という職業をテーマにしているので、いつか映画が作られたとしても、小説バージョンが一番楽しめると確信しています。
3. ”La Valse aux Adieux” by Milan Kundera
感想の記事でも書きましたが、登場人物の心理描写が面白かったです。プラハのある地区が舞台となっているのですが、プラハの旅行を少し思い出して懐かしくもありました。
この本の感想を書いた記事では紹介しなかったフレーズがあるので、ここで紹介したいと思います。人生の予測不可能性について、です。「….Je veux dire par là qu’accepter la vie telle qu’elle nous est donnée, c’est accepter l’imprévisible. Et un enfant, c’est la quintessence de l’imprévisible. Un enfant, c’est l’imprévisibilité. Vous ne savez pas ce qu’il deviendra, ce qu’il vous apportera, et c’est justement pour cela qu’il faut l’accepter.(…自分がここで言いたいのは、人生を与えられたように受け入れるというのは、予測できないということを受け入れること。そして、子供というのは、予測不可能の本質。子供こそが予測不可能。その子供が何になるのか、何をあなたにもたらすのか、分からない。だからこそ、その予測不可能を受け入れなくてはならない)」とても深い文章だと思います。不意打ちを避けるため、予測不可能はなるべく避けたいものですが、人生で予測不可能な出来事は多いと思います。
1. ”Les Derniers Jours de Nos Pères” by Joël Dicker
フランスで大きな賞をもらった「La vérité sur L’Affaire Harry Quebert」を最初に読み、とても興味を持ちました。この小説がとても気に入り、これを超えるのは難しいだろうと勝手に思い込んでいました。今のところ、この著者の出版作品は2冊だけですが、個人的には最初に書かれた”Les Derniers Jours de Nos Pères”の方が気に入っています。第二次世界大戦中、と時代、そしてテーマ自体も重く決して笑えるような話ではありません。が、「究極の選択」というテーマが作品中何度も出てきて、色々考えさせられます。自分ならこの状況で何を犠牲にして、どちらを選ぶのかということを読みながら、何度も考えました。次回どんな作品を書いてくれるのか、今からワクワクしています。次回作が存在するかどうかさえもまだ分かりませんが、この2作品で終わらないことを大きく期待しています。
2. ”Saga” by Tonio Benacquista
彼の作品はいくつか読みましたが、この「Saga」がずば抜けて面白いと思います。あり得ない結末だけれど、テレビ業界を面白く(皮肉を込めて)描いていました。笑えるシーンでも「よく考えてみたら、結構深刻なことかも」と思わされてしまいました。
最近では、色々な小説が映画化されています。が、これは脚本家という職業をテーマにしているので、いつか映画が作られたとしても、小説バージョンが一番楽しめると確信しています。
3. ”La Valse aux Adieux” by Milan Kundera
感想の記事でも書きましたが、登場人物の心理描写が面白かったです。プラハのある地区が舞台となっているのですが、プラハの旅行を少し思い出して懐かしくもありました。
この本の感想を書いた記事では紹介しなかったフレーズがあるので、ここで紹介したいと思います。人生の予測不可能性について、です。「….Je veux dire par là qu’accepter la vie telle qu’elle nous est donnée, c’est accepter l’imprévisible. Et un enfant, c’est la quintessence de l’imprévisible. Un enfant, c’est l’imprévisibilité. Vous ne savez pas ce qu’il deviendra, ce qu’il vous apportera, et c’est justement pour cela qu’il faut l’accepter.(…自分がここで言いたいのは、人生を与えられたように受け入れるというのは、予測できないということを受け入れること。そして、子供というのは、予測不可能の本質。子供こそが予測不可能。その子供が何になるのか、何をあなたにもたらすのか、分からない。だからこそ、その予測不可能を受け入れなくてはならない)」とても深い文章だと思います。不意打ちを避けるため、予測不可能はなるべく避けたいものですが、人生で予測不可能な出来事は多いと思います。
夏の読書 番外編 [読書’13]
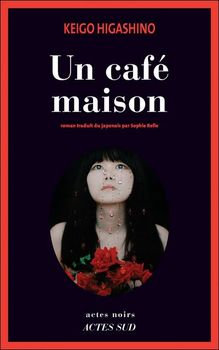
今回は番外編と称して、スイス人が読んだ日本の小説について少し書いていきたいと思います。ホストファザーの誕生日が7月下旬だったので、東野圭吾のUn Café Maison(聖女の救済)をプレゼントしました。同著者の「容疑者Xの献身」も読んでいて面白かった、と言っていたので、今回の作品の感想も気になるところでした。個人的には「聖女の救済」のトリックの意外性が気に入りました。ホストマザーもこの作品を夏休み中に読み、2人から感想を聞くことが出来てとても興味深かったです。
①室内でいちいちスリッパを替えるのにびっくり
アメリカでは室内を外靴で歩き回るというイメージですが、私が知っている多くのヨーロッパ家庭では「スリッパ」(サンダル)に玄関で履き替えます。と言っても、日本のような玄関(家の入り口の段差)があるわけではないので、基本土足禁止の部屋も急いでいる時は外靴でドカドカと入っていく人が多いです。
ホストファミリー宅は基本2階が土足禁止。それ以外は結構曖昧ですが、入り口で裸足になるか室内履きに履き替えます。そんなホストファミリーですが、日本のトイレ用のスリッパにはびっくりしたようです。札幌の我が家ではスリッパもなく裸足ですが、祖父母の家では室内スリッパ、トイレスリッパと分かれています。ヨーロッパ人からすると「同じ室内なのにそこまで徹底する?」というイメージのようです。
この小説内で、トイレスリッパが登場したことさえ自分では覚えていないのですが、スイス人からすると相当な衝撃だったみたいです。小説内で一番驚いたのがこのトイレスリッパ、とさえ言っていました。
②日本でのパッチワークにびっくり
小説内の登場人物がパッチワークを習っているという設定があります。スイス人からすると、「なぜ日本でパッチワーク?」と思うようです。言われてみると、日本のどこの文化教室でもパッチワークのクラスは存在します。なぜヨーロッパ(イギリス)のものが日本で流行っているのか、そこまでは分かりません。
③殺人のやり方まで日本人らしい
最初このように言われた時は、何が言いたいのかさっぱり分かりませんでした。ホストファミリー曰く、「ヨーロッパ人からすると『日本人は完璧に/きっちり仕事をする』というイメージが強い」とのことでした。銃を使う、という派手な演出は無くても、完璧な(そして殺人現場を全く汚さない毒殺)事件が彼らのイメージする「仕事を完璧にやる」日本人にぴったり合っているようです。
こういった感想を聞くとは思っておらず、私にとってもびっくりの本でした。
夏の読書 その16 [読書’13]
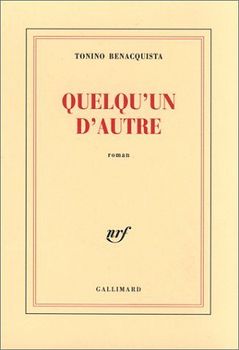
この夏一番読んだ作家が、Tonio Benacquistaでした。彼の「Quelqu’un d’Autre」を読みましたが、少々がっかり。
2人の男性が3年後までに別人になれるかどうか、という賭をし、その様子が描かれています。2人が様々な手段を使って(仕事を変える、ガールフレンドと別れる、新しい身分証明書を作る)別人へと近づいていきます。が、あまり興味のないテーマだったので、読んでいても少し退屈してしまいました。なんとか読み終えた、という感覚が大きく残ったままでした。
それでも面白かったのは、二人が新しい名前を選ぶシーン。賭けのため、各自で新しい名前を選んでいきます。Vから始まる変わった名前を選んだり、となかなか面白かったです。また、自分がもし名前を選べるとしたら、と名前についても考えてしまいました。
ヨーロッパ人はよく複数の名前を持っています。名前、ニックネーム、セカンドネームなどなど。スペインでは母方の名字を「第二の姓」として使うこともあります。歴史上の人物のように、長い名前は今でこそ見なくなりましたが、日本人の名前に比べると長い人が多いです。小さい頃はセカンドネームを持っている人をうらやましいと思っていました。単なる無いものねだりですが、変わったことを考えていたものだ、と今では感じます。ただ、このセカンドネーム、ヨーロッパで使う人はほとんど居ません。ニックネームと組み合わせて使う人も居ますが、セカンドネームだけで呼ばれている人は、私の知り合いにも居ません。
ニックネームは名前が長い場合作られることが多いようですが、自分で勝手に作る人も居ます。例えば韓国人の中で、韓国語の名前が「ジェール」という人が言いました。英語の「jail(刑務所)」と同じ発音なので、Jamesという英語名を持っていました。中国語や韓国語の名前は発音しづらいので、英語の授業の始めに自分の「英語名」を選ぶという人が多いようです。
ちなみに、このブログ名のAmyも自分の英語名から来ています。フランス語ではアルファベットの書き方を少し変えれば、自分の名前は日本語と同じ発音になるので、Amyという英語名はほとんど使わなくなってしまいましたが。
夏の読書 その15 [読書’13]

今回紹介するのも、あまり馴染みの無い国の作家。Le vieux qui lisait des romans d’amour(ラブ・ストーリーを読む老人)という作品です。チリの小説家Luis Sepúlvedaという人が書いたものです。スペイン語の授業でスペイン語の短編小説(本当に短い話)を何度か読んだことがありますが、それ以外でスペイン語圏の小説に触れたことはありませんでした。理想は原語であるスペイン語で読むことですが、結局フランス語で読んでしまいました。ちなみにこの作家、この作品のフランス語訳が驚異的なヒットを記録して有名になったらしいです。フランス語訳も悪くはない、ということなのでしょうか。
原語で読んでいないので一概の比較は出来ませんが、フランス語訳を読むのは不思議な感覚でした。フランス語で書かれていても、スペイン語圏らしい雰囲気が出ていると感じました。私が持つスペイン語圏の人のイメージは「とにかくよく喋る」なのですが、小説内の会話のシーンではまあ会話が多い!本当におしゃべり好きな人たちだと実感します。
「ラブ・ストーリーを読む老人」という変わったタイトルではありますが、結構政治的な内容も含まれています。これも政治を語るのが好きなフランス語圏の人たちに好かれた理由の一つでしょうか。この小説家、政治犯として投獄生活も送ったことがあるようです。彼のこういった経験も小説に強く影響していると思います。印象に残っているシーンは選挙期間。主人公の老人は森林に住んでいて、社会との接触はほとんどありません。ある日街に行き選挙があることを知り、「投票する権利がある」と教えられます。そしてこの老人は「その『権利』とはどこで買えるのか?」という質問をします。このシーンが、自分には衝撃的でした。自分には当たり前に存在している物が、他人にとっては未知の世界。投票の権利、購入する必要はないけれど、世界の多くの場所では購入する以上に難しい行為が投票だと思います。このシーンを読みながらそんなことを考えてしまいました。
夏の読書 その14 [読書’13]
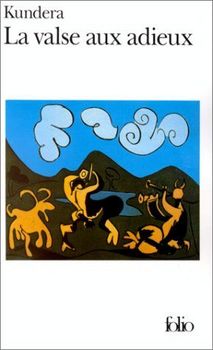
今回紹介するのはミラン・クンデラの「La valse aux adieux(別れのワルツ)」です。チェコの本を読むとは思っておらず、自分でもびっくりでした。もちろん、チェコ語は分からないのでフランス語でしたが。名前は何となく聞いたことがありましたが、本屋へ行って最初に手に取るような小説家では決してなかったと思います。
それほど縁が無い本でしたが、読むことが出来た本当に良かったです。ホストシスターが夏の初めに読んでいて、ホストマザーもつい最近まで彼の作品を読んでいました。私も次は何を読もうか、と思っていたところでした。本当にテキトーに手に取った小説でしたが、読みながらグングン引き込まれてしまいました。話も自分好みではなく、読みながら「自分の好きなジャンルでは無いのに、なぜこれほど引き込まれるのだろう」と思い、その「なぜ」を知るために読み切ったと言っても過言ではないかもしれません。結局読み終わってもその「なぜ」は分からなかったのですが。
各登場人物、少し変わっているのですが、決して現実世界に居ても不思議ではない人たちでした。この登場人物達の数日間が描かれているのですが、心理描写が面白いです。登場人物の心理描写が上手い作品はいくつかあります。が、的確過ぎると、自分の心理を見透かされているような気がして、ちょっと変な気分になります。そのため、的確過ぎる心理描写は個人的にあまり好きではありません。が、この小説の心理描写は 、「分かる、そういう表現は自分でしないけれど 」という微妙なさじ加減が良かったです。読者(自分)とは異なる表現の仕方、しかし分かりやすい表現が多かったです。
本自体も面白かったのですが、出版までの経緯もまた興味深かったです。基本、小説は原語で読むように努力し、翻訳にはなるべく頼らないようにしています(自分の知っている言語で書かれた場合のみ)。もちろん、翻訳にも素晴らしい作品があると思いますが、やはり作者自身が書いた言葉で理解したいという気持ちが強いので、オリジナルを読むようにしています。が、今回のように自分の全く知らない言語で書かれた場合は、翻訳に頼ることになります。しかし、この小説、完全に「翻訳」とは言えないようです。というのも、ミラン・クンデラはフランスの市民権を取得し、今ではフランス語で執筆することもあるほどだそうです。この「別れのワルツ」も最初はチェコ語で書かれ、他の小説同様、フランス人がフランス語に訳して出版。そして1985~1987年の間、クンデラ自身がその訳を見直して、また新しく出版された、という経緯があるようです。私が読んだのはその、「著者によって見直された」版です。最初のフランス語初版を読んだことがないので、比較することは出来ません。が、著者がどの部分をどう(納得せず)改訂したのか少し気になるところです。
夏の読書 その13 [読書’13]

Lyonから帰ってきて読んだ本が、Saint-Exupéry(サンテグジュペリ)の「Vol de nuit(夜間飛行)」でした。彼の像、正確には「星の王子様」の像を見て、彼の作品を読みたいなあと思ったからです。「星の王子様」以外彼の作品は読んだことがなかったので良い機会でした。
「星の王子様」も中学生の 頃に読んで結構印象に残っています。理由はよく分かりませんが、特に1日1回ガス灯の点灯と消灯をするおじさん、王子様の持っているバラが衝撃な印象として残っています。今回読んだ「夜間飛行」も面白かったです。個人的には、「星の王子様」より好きな作品です。
夜間だけ運行する、郵便飛行の事務室が舞台となっています。ヨーロッパから、当時(1930年頃)電灯がほとんどない南アメリカ(パタゴニア)に向かう飛行機を迎えるRivière支配人を中心とした話です。部下やパイロットにとっても厳しく、冷たい彼ですが、実はこの態度、パイロットの安全を一番に考えた結果とる態度でもあります。が、そんなことを他人は知りません。彼の表向きの態度と内面の葛藤が上手く表現されていました。飛行や空の描写だけでなく、内面の表現が素晴らしく、1日で読み終わってしまいました。
あるドラマで「空は女のように気まぐれ」というセリフをパイロットが言っていました。女性が気まぐれかどうかは別として、空は本当に気まぐれだと思います。その気まぐれに反する形で、重たい鉄の塊(=飛行機)が空中に浮き、ある方向に向かう、ということ自体、よく考えてみると無茶な考えのような気がします。その気まぐれに上手く対抗して、頻繁に飛行機が行き来する今の時代を見ると、本当にすごいと思います。
更にこの小説内でパイロットが飛ぶのは何も見えない夜間。夜間という闇に対する恐怖はもちろん、各パイロット持っていると思います。が、それを超えてまで飛ぼう、と思うのはなぜなのか気になります。任務意識からなのか、純粋に空が好きだから飛ぶのか。 私は飛行機が好きですが、真っ暗の中飛ぶのは好きかと聞かれると、答えに困ります。
この本の中で気に入ったセリフはこちら。Rivière支配人が部下のRobineauに言うセリフです「Voyez-vous, Robineau, dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : Il faut les créer et les solutions suivent.」(ごらん、Robineau。人生に解決方法はないんだ。前進させる力があって、その力を作り出し、解決方法はそれに付いてくるだけ)。解決方法以前にそれを実行する力があるかないか、それを作り出せるかが問題、ということだと思います。思い当たる経験が自分にもあるので、このセリフを見た時は「その通り!」と思ってしまいました。
夏休み中に読んだ作品でマイベスト3を作る予定でいたのですが、選考が難しくなってきました。この
夏休み読書企画、まだ続きます。
夏の読書 その12 [読書’13]
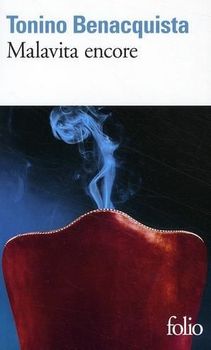
クリスマスにもらったMalavitaを冬休み中に読みました。その続編を読んでみました。前作もまあまあ面白かったのですが、著者の表現スタイルに慣れてきたのか、以前よりスラスラ読めました。そのせいか、前作以上に楽しんだ、という感覚が読み終わってから残っていました。
前作と登場人物は同じ、Witsecと呼ばれるFBIの証人保護プログラムの下で暮らすイタリア系アメリカ人の家族。アメリカからの追跡を逃れるため、フランスで生活するという設定は以前と変わりません。が、時が経って、父親のせいで生活がWitsecによって拘束されていると家族は感じるようになります(自分の過去を話せないなど)。そのため、母親、姉、弟各自で自分の生活を「独立させよう」と悪戦苦闘する様子が描かれています。FBIがそういったことを許すのか、とちょっと気になったのですが、そこは小説。意外と家族のメンバーには寛大で、なるべく「普通」の生活が出来るように助けているようでした。「保護プログラム」というと、かなり守られた生活だというイメージがあったのですが、目立たないためにも他人と変わらない生活を心がけているようです。が、自分の過去を話したくても話したくないというのは、苦労が多いと思います。
最後は少しあっけなく終わってしまいました。続編が今のところ出ていないので、今のところ、この作品が完結版ということです。次回作が出ても良し、このまま終わっても良し、という感じでした。
夏の読書 その11 [読書’13]
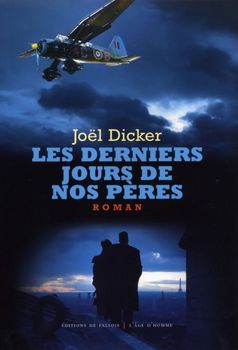
今のところ、自分の夏の読書トップに入っているJoël DickerのLa Vérité sur l’Affaire Harry Quebertを読んで1週間後、彼の作品をもっと読んでみたいという気になり、図書館で彼の他の作品を借りてみました(今のところ出版しているのは、2作品のみ)。どの図書館も貸し出されていて、予約をしなくてはなりませんでした。日本の便利な図書館と異なり、予約する図書館を指定出来ないので、どこの図書館が予約してくれるかどうかは運次第。ラッキーなことに自分が行く図書館で予約が取れたので、早速読んでみました。
タイトルとは「Les Derniers Jours de Nos Pères」(私たちの父親の最後の日々)と悲しい題がつけられています。SOE(Special Office Executive)という第二次世界大戦中に活躍したイギリスの特殊戦争執行部が舞台となっています。フランスのレジスタンスとして活動するため、イギリスの特殊部隊で訓練を受ける若者達が主人公となっています。傍聴、隠れ家の確保などスパイに関することを多く学びます。10人以上の主要人物が居るため、名前と特徴を書いたお手製のメモが欠かせませんでした。
最初の100ページはこの訓練での出来事が多く書かれ、あまり興味はわきませんでした。が、訓練を受け実際にフランス、イギリス各地に派遣されると一気にストーリーが興味深くなっていきました。また、主人公(だと思っていた)Palの父親はパリに住んでいるのですが、その出来事も少しずつ描かれています。一昨年前私が住んでいた場所、そして通っていた学校の近くにこの父親も住んでいるため、話の中に登場する通り名も馴染みのあるものばかりでした。
フランスのスパイを探るため、ナチス軍のスパイもパリに乗り込んできています。SOEがメインなので、ナチス軍側のスパイは一人を除いてほとんど登場しません。が、そのナチス軍のスパイも一人の人間として書かれていました。イギリス、フランス、ドイツ、と属している場所は異なっていても、各自様々な個人事情を抱えていて、そういったことに焦点が当てられていました。戦争が原因で敵対する仲であったけれど、個人として見てみると皆「家族のため」に行動していることがよく分かります。
訓練中はPalに焦点が当てられ、常に三人称ではありますが、彼の視点からほとんどのことが語られていました。が、第二部に突入すると彼の父親など、Pal以外の視点も多く入ってくるようになってきました。Palが主人公だと思っていた私はちょっと驚いてしまいましたが、タイトルを見直してみると納得。なぜ、「私」ではなく、「私たち」と複数になっているのかがよく分かります。
前回読んだ本が、かなりの評判だったため、処女作を読むのを少しためらってしまいました。2作目ほど面白くなかったら、と余計な心配をしてしまいました。2作目同様テーマは重いです。だからこそ、ホッとする場面、ちょっとした心温まる部分は読んでいて本当に嬉しくなります。2作目同様、一気に読み終わってしまいました。ただ、この作家まだ2作しか出版していないので、これで彼の作品を全て読んだことになります。次回作が発表するまで、彼の作品は読めない、これが唯一、この本を読んで残念だった点かもしれません。
夏の読書 その10 [読書’13]

(本の写真がないので、ローザンヌの風景。電車で通過しただけですが)以前読んだ本に引き続き、今回もスイスで話題になった作家の本を読みました。Max Lobeの「 L'enfant du Miracle」です。ローザンヌ大学で勉強するカメルーン出身の学生、Paulの話です。カメルーンで行われる伝統儀式や生活、ローザンヌ大学での生活が交互に描かれていました。伝統儀式(特に妊娠しづらい女性を「治療する」儀式)は異常なものが多く、読んでいてとても怖かったです。が、ローザンヌ大学での学生生活は自分にも身近なものが多く、読み進めていくのが面白かったです。
ローザンヌ大学で主人公は学生アパートに住んでいます。各自個室、そして共同キッチンという形になっているようです。ジュネーブ同様、ローザンヌも世界各国から留学生が来ているみたいです。主人公と仲が良いのは台湾から来たEyangoという留学生。彼らのやりとりは、自分も経験したことがあるので「そう、その通り!」と思いながら読んでいました。例えば、Eyango、自己紹介をする時、台湾出身であることを強調します(中国ではなく、と)。が、台湾から遠いカメルーンから来たPaulにとっては大差がありません。私も自己紹介で日本出身、と言っても、ヨーロッパ人からすると「地図の端にある国」というイメージしかないみたいです。日本に興味がある人は別ですが、アジア諸国は遠すぎてよく違いが分からない、という人がヨーロッパには多いみたいです。
この本を紹介してくれたスイス人も「本の中に変わった日本人の留学生が出てくるから!」と予告してくれました。が、いくら読み進めても、変な日本人学生は登場しません。出てくるのは変な台湾人学生、Eyangoだけ。他にも変わった留学生は登場しますが、アジアっぽいのは彼だけ。読み終わってから「話していた変な学生ってEyangoのこと?」と聞いてみると、私の予感は的中。台湾と日本を混同していたみたいです。
先ほども書いたように学生生活部分はスラスラと読み進めることが出来ました。が、カメルーンの生活は変わった名前や身近ではない伝統儀式の描写が続き、読み進めるのに苦労しました。200ページ足らずと短い本なのですが、読み終えるのに少し時間がかかりました。読破するのに苦労した、という印象が最後まで残ってしまった作品でした。



