「翔ぶが如く」(by 司馬遼太郎:1972) [読書’15]
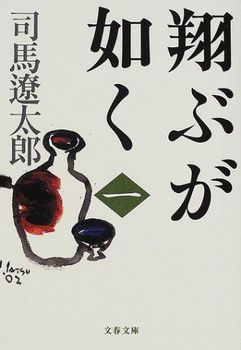
歴史小説/マンガは長期休暇に読む物、と決めています。時間があるということと、寝不足の日が続くからです。マンガの「三国志」は中3の春休み、「竜馬がゆく」は大1の夏休みに読みました。どちらもかなりの大作で、休み中といえども、読み終わるのに結構時間がかかったと記憶しています。今回の夏休み(前半は教習所通いでしたが)にも、新たに歴史小説に挑戦してみることにしました。司馬遼太郎作品はいくつか読んでいるのですが、大作で読んでないものが結構あります。サラリーマンや政治家の間で人気の「坂の上の雲」か「翔ぶが如く」のどちらかを読んでみようと思っていました。父が「翔ぶが如く」を読んでいたので、遅れて私も読み始めました。
文庫本10冊なので、かなりの長さでした。そのため、最終巻を読破した時には「終わってしまった」というより、「終わって一息つける」気持ちの方が大きかったです。明治初期の10年、大久保利通に言わせると「創業の時期」が描かれています。単純計算すると1年の出来事が1冊(約300ページ)ごと描かれているので、かなり密度の濃い作品でした。しかし、当時の社会に勢いがあって、作品の密度が濃くなっているのではなく、どちらかというと「終わり」へ向かっているような寂しさがありました。私が以前に読んだ司馬遼太郎作品は、戦国、幕末のものだったので、各作品に一種の勢いがあった気がします。しかし、「翔ぶが如く」の序盤では、倒幕で活躍した坂本龍馬を始めとするあの人、この人は既に居なくなってしまっている感じがあり、後半では明治後のあの人もこの人も病気で亡くなってしまい、寂しくなってしまいました。
「翔ぶが如く」は西南戦争前後の日本が描かれているので、鹿児島も多く登場します。妹が鹿児島に住んでいるので、いくつか知っている地名も出てきました。妹の住んでいる近所はかなり田舎なのですが、そういった場所が歴史的な出来事の舞台になったりしていて、びっくりしました。歴史の短い北海道に住んでいると、歴史的瞬間の土地というものを感じることがないので、ちょっとうらやましいです。北海道で歴史的に重要な場所と強いて言えば、土方歳三が戦った箱館戦争でしょうか。
また、初めて鹿児島へ行ったときにも感じたことなのですが、鹿児島での西郷隆盛に対する根強い人気は明治維新から来ている、ということを、改めてこの本を通じて再認識しました。土産に始まり、鹿児島市のあちらこちらに西郷隆盛があってびっくりしました。学校の歴史の授業では、どちらかというと「西南戦争を起こした人」という風に教えられたと記憶していますが、鹿児島の人は異なるとらえ方をしている気がします。当時は更にインターネットも存在していない時代。西郷隆盛の姿を知っている人はほとんどおらず、各自独自のイメージを持っていたようです。「あの人が西郷隆盛だとは知らなかった」という話も多くあり、そのために出来事が動いたこともあったようでした。
長く、密度の濃い小説でした。
A Time to Kill (by John Grisham:1989) [読書’15]
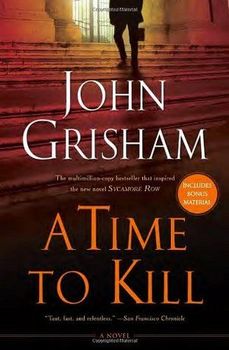
同タイトルで映画(邦題は「評決のとき」)も公開されている作品です。2ヶ月ほど前、アメリカ人の友人がロースクールへの進学が決まり、一緒にご飯を食べました。彼女は弁護士になるつもりは今のところないようですが、「弁護士って具体的にどんな仕事をするのか」と彼女と話をしながら疑問に思いました。弁護士の仕事を知るため、手軽に読めそうな法廷サスペンスを検索したところ、この作品が出てきました。
ミシシッピ州(南部の州)で、13歳の黒人少女が白人主義者の若者2人に強姦され、その若者達を少女の父親が銃殺。その父親を(白人の)弁護士が弁護するというストーリーです。時代について明確な描写はありませんが、KKKが当たり前のように登場してくるので、戦後で1960年よりは前という感じでしょうか。私は最初の数章で、父親に肩入れしているので、「ひどい!」と思いながら読んでいました。通常の「正義」が通用しないこの州で、どう弁護していくのかという、弁護士の準備段階が細かく描かれています。父親を弁護するのだから、彼の経歴や銃殺が行った状況などを詳しく弁護士が調べていくものだと私は思っていました。しかし、彼自身についてはほどんど調査しません。なぜならこの裁判で鍵を握るのは、陪審員制度。一般市民が有罪か無罪かという重要な判断を下します。この作家、元弁護士ということだけあって、ミシシッピ州の陪審員制度について詳しく描かれています。実際の法廷に登場するのは5〜6人ほどの陪審員ですが、そのリストに挙げられる人、リストに入れられる可能性がある人、といくつかの選考過程があります。被告人以上に、この陪審員候補に対する素性チェックを、弁護士は細かく行っていました。読んでいても、誰の裁判か忘れてしまいそうなほど、陪審員候補について調べていきます。本の返却日ギリギリまでかかって読みましたが、飽きませんでした。特に最後の法廷シーンは、説得力のある話し方というのは、こういうことか、と再認識出来るものです。映像化された作品ということで、映画はどのような感じになっているのか、一度見てみたいと思いました。
にっぽん三銃士(by 五木寛之:1974) [読書’15]

父にこの作家を薦められ、作家の作品一覧を検索し、デュマの「三銃士」にタイトルが似ているからという理由でこの作品を選び、読んでみました。
ロードムービー(旅の途中で起きる出来事が物語になっている映画)のような感じで、色々な場所が登場します。東京、博多、京都などなど。小説に登場する博多は、以前行った時に抱いたイメージとあまり変わらない気がしました。しかし、小説に登場する東京は、私の抱くイメージからかけ離れていました。1960年後半から70年代の、様々な運動が活発だった時が舞台となっているこの小説。新宿の広場で、デモのような運動があったり、私の知っている新宿のイメージとはかけ離れていました。表参道ほどではないけれど、新宿もどちらかというと「おしゃれ」なイメージが私にはあるので、乱闘があったり、いきなり歌を歌ったりする場所となっている新宿の様子にはびっくりでした。もしかしたら、新宿はビルがたくさん建っていて都会という感じがするため、私にとって「おしゃれ」に感じるのかもしれませんが。
「三銃士」というと、デュマの原作に登場するダルタニアンを私はイメージします。3人の中で、一番年下、カッとなりやすく勢いがある人物です。そのため、この「にっぽん三銃士」でも勢いをちょっと期待してしまっていました。しかし、登場人物はちょっと中年の男性3人なので、所々ブレーキがかかっている感じが若干しました。変なところでブレーキがかかり、でもその心理的ブレーキについて、自分なりの見解を色々示すところは笑えました。
夏と言えば [読書’15]

(余市の海です)
夏休みも本格的に始まり、テレビでも夏休み特集が組まれています。少し前まで、夏と言えば海水浴、だったようですが、私は夏の海水浴と無縁の夏休みを過ごしてきました。毎年色々な夏休みイベントがあったけれど、共通して長年あったのは、水泳の朝練・夕方練習(=夕練)です。そのため、水泳を辞めてもう5年以上経つけれど、夏休みというと、どうしても「水泳の朝練・夕練、合宿」のイメージです。
さて、他にも夏と言えば、私の好きなアイスはもちろん、ここ数年は村上春樹の本も欠かせなくなってきました。ここ数年(特に日本に居る時)、夏にどんな本を読んだのか思い出してみると、必ず村上春樹の本を読んでいます。私は村上春樹のエッセーが好きなのですが、小説も読みます。
今年の夏に読んだ彼のエッセーは、「遠い太鼓」です。ギリシャやイタリアでの生活を描いたエッセーです。1986年から89年の3年間の生活なので、「ちょっと昔」の話かもしれません。ユーロという通貨ももちろん出回っていなくて、私が知らないヨーロッパという感じでした。ギリシャ人とのやりとりも登場しますが、国民性というかギリシャ人の性格を垣間見ることが出来ました。この本を読んだ時、ちょうどギリシャのEU財政緊縮策に対する国民投票が行われていました。作者の見たギリシャ人の性格と、今日の財政緊縮策に対するギリシャ人の反応を見ていると、変わっていない部分も多くあるのだ、と感じました。私はギリシャ人の知り合いが居ないので、本当のところは分かりませんが。
そして、イタリア編で印象に残っているのは車!教習所に通っている間に読んだ本であるせいか、車の印象が強いのかもしれません。イタリアの都市は(フランスと同じように)駐車スペースがないので、どれだけ上手に縦列駐車を出来るかが結構重要なようです。確かに、これは今でも変わっていないかもしれません。縦列駐車かどうかは分かりませんが、イタリアではほとんど隙間なくずらっと車が路駐されていました。車道の運転は結構乱暴というか、走っている車を見てもいまいちルールが分からないので、歩行者としては結構怖い思いをしました。
また、「像の消滅(L’éléphant s’évapore))という短編集も読みました。本のタイトルとなった作品は、個人的に面白いとは思いませんでした。一番面白かったのは「パン屋再襲撃(La seconde attaque de boulangerie)」でした。タイトルにまず惹かれました。また、内容も、ちょっとコメディ映画っぽく、笑ってしまいました。ファンタジーではないけれど、あり得ない設定が多く、笑えました。
また、一番怖かったのは「踊る小人(La nain qui danse)」という作品です。これは日本語でも読んだことがあったのですが、読んだ日は眠れませんでした。怖い映画やテレビを見て、または怖い話を聞いて寝られないということは以前にもあったのですが、怖い本を読んで寝られないということはこの作品が初めてでした。それぐらい怖かったのですが、不思議なことに話の内容はほとんど忘れてしまっていました。が、今回タイトルを見て「夜に寝られなかったあの作品だ」とすぐに思い出しました。フランス語で読んでも怖さは変わりませんでした。ただ、どこの部分が怖いのか、と聞かれても困ります。話を要約するとそれほど怖い話ではないのです。あくまでも、「読んだら怖い」作品です。
Underground :The Tokyo Gas Attack and the Japanese Psyche (by Haruki Murakami:2000) [読書’15]
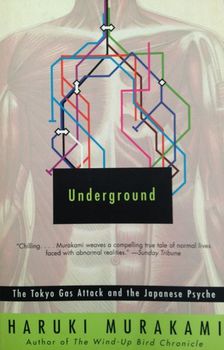
原題は「アンダーグラウンド」、地下鉄サリン事件の被害者、関係者のインタビューを元に書かれた作品です。この本は、ずっと読もうと思っていて、機会を逃していました。というのも、スイスやフランスでは、 この地下鉄サリン事件について、結構詳しく知っている人が居てびっくりしたのです。事件の背景、起きた時刻や場所も詳しく知っていて、「それほど大規模に海外のニュースでも取り上げられたのか」と最初は思っていました。しかし後々、村上春樹がこのインタビュー集を出していたのが大きな理由だということに気づかされます。そこで、彼の作品を英語で読んでみたらどんな感じなのか、と思い、今回は英語で読んでみました。
この作品では、インタビューをまとめて、一連の事件を描いていました。単に、「○時○分に、△線で、事件が発生した」という事実が語られるだけより、より説得力がありました。例えば、最初にホームの不審物に気づいた駅員Aさんの行動が描かれ(別の駅員に連絡し、到着した車内で倒れている人を目撃しetc)、次の章では駅員Aさんから連絡を受けた駅員Bさんの行動が描かれ、更に車内に居た乗客からの視線、と事件に巻き込まれた様々な人の視点からこの事件を追っていきます。もちろん、見方によって異なる部分はあるけれど、一致している部分も多くあり、この部分は単に何が起こったかを伝えられるより、更に説得力がある気がしました。序章に作者が「本当に何が起こり、その時そこにいた人が何を感じ、見たのか」を知りたいというのが本を書くきっかけというようなこと書いていました。まさに、事件に巻き込まれた人(そしてインタビューを受けることを許可した人)が一つの出来事、話を語っていくという形でした。
後半部分は、オウム真理教の元信者達へのインタビューでした。こちらはどちらかというと、地下鉄サリン事件というよりかは、オウム真理教内でどんなことが起こっていたのかという全体像がインタビューから見えてくるという感じでした。
私は地下鉄サリン事件が起きた当時については、小さかったせいかあまり覚えていません。東京がどれほど都会であるかということも、漠然としたイメージしか持っていませんでした。ただ、東京で実際地下鉄やJRに乗って通学した経験がある今、この事件に関する本を読んでみると、ゾッとします。時期は異なっていても、この事件に巻き込まれた人達と同じように、私もほぼ毎日同じ地下鉄/JRに乗って、また乗り換えが便利な特定の車両に乗って通学していたからです。良いノン・フィクションの作品を読むことが出来ました。
「峠」(by 司馬遼太郎:1968)、「最後の将軍-徳川慶喜-」(by 司馬遼太郎:1966) [読書’15]
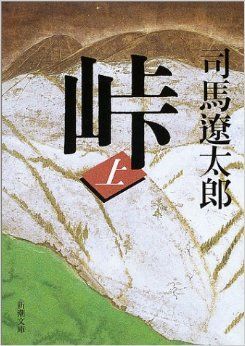
両作品に登場する人物がもし、違う藩に生まれていたら、もっと実力を発揮できたのではないか、と思わずにはいられない作品でした。「峠」は長岡藩の河井継之助、「最後の将軍」は徳川慶喜を扱っており、両作品幕末に登場した人物を扱っています。長岡藩は小さく、地の利にも恵まれていないということを自覚し、対策を練った河井継之助がもし、江戸に生まれて当時の日本を考える立場に居たらどうなっていたのか。また、読みが鋭い徳川慶喜がもし幕府の生まれではなく、反幕府側だったら、ということを何度もこれらの本を読みながら考えてしまいました。
河井継之助については、ほとんど知りませんでした。以前、妹のインターハイ応援で行った新潟県で、河井継之助の記念館へ行きました。彼についてはほとんど知らなかったので、記念館では「新潟県は結構歴史があったのだ。この人は新潟県で重要な人なのかな」と思ったぐらいでした。父から薦められてこの「峠」を読んでみたのですが、新潟県(当時は長岡藩)という言葉でくくることが出来ないほど規模の大きな人でした。彼がやったことは結果的に藩を考えてのことですが、当時としてはかなり最先端の技術、考え方を用いた藩政治を行っていたようです。特に出会ったスイスの商人からは大きな影響を受けているようでした。その商人の話からしか当時のスイスというものが、私達には分かりません。しかし、その様子を文中で読んでいく限り、今のスイス人とあまり変わっていない考え方もあるようでした。例えば、小さい国で自然資源もない「貧しい」国であるという自覚。私のスイス人の友人も「スイスは海に面していないし、かといって自然資源があるわけでもないし、小さい国だし」とよく言っていました。だから中立の立場で、自国を守ることが大切だ、ということなのだと思います。この考え方が2世紀近く前から共有されている物だということを、「峠」を読みながら感じました。
この「峠」を読んだ後に、幕府側の話、「最後の将軍」を読みました。今まで反幕府側の話を読んできたので、幕府に共感出来るかどうか心配なところはありました。しかしそこは、司馬遼太郎の文章力。幕府には共感出来なくても、最後の将軍、徳川慶喜はちょっとかわいそうだと思ってしまいました。物事を読み取る力というのはかなり優れていたようで、もし彼が参謀のような立場だったら、違う形で大きく歴史に名を残していたのではないか、とこの作品を読みながら思ってしまいました。
全く別の立場の人間を扱った2作品を読みましたが、読み終えた後には似たようなことを考えてしまいました。
恋に落ちて(アンソロジー/村上 春樹訳:2013) [読書’15]
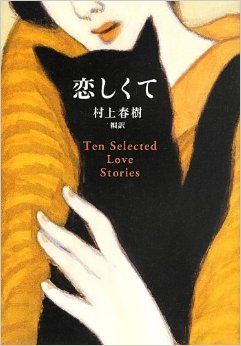
先月、村上春樹が翻訳した本を読み、結構気に入ったので、別の翻訳作品も読んでみることにしました。父が以前読んでいた、とこの本を思い出し、図書館で借りてきました。
ダントツで気に入ったのは「愛する二人に代わって」でした。本の最初に出てきた作品でしたが、最後まで印象に残っていました。個人的に、この作品を越えるものは残念ながらこの本にはありませんでした。ストーリーは衝撃的、というほどではないのですが、アメリカの9.11後という時代背景、代理結婚というシステムを上手くストーリーに組み込んだ話だと思いました。また、映画にしても面白い作品だろうな、と思いました。心理的駆け引きというよりは、二人が代理人として市役所で結婚式を挙げる、という図式がこのストーリーで重要なので、映像化出来そうな作品だと私は思いました。
また、この本の最後に入っていた「恋するザムザ」は、英語と日本語の両方で読んでみたので、表現という点で面白かったです。長編だと時間がかかってしまうので、このようなことはしないのですが、短編なので両言語で読んでみようと思ったのでした。最初に英語で読んだので、日本語で読む際は、各登場人物の雰囲気が既に出来上がっていました。改めて日本語で読んでみると、ちょっと雰囲気が違っていてびっくりしました。特に女の子のしゃべり方が、思っていた以上にばっさり(でもきつい感じはしない)としていました。読み方が甘かったかな、と最初は思ったのですが、この差は語尾からでした。多分、英語で雰囲気の違いを出すとなると、本の世界では語彙で変化をつけるしかないと思います。しかし、日本語には語尾を変えるという便利な表現方法があるので、ちょっと語尾を変えるだけで雰囲気に違いが出ます。同じ女の子でも、「〜だろう」というのと「〜でしょ」では大きく印象が異なります。そのため、英語版を読んでいて私が想像していた女の子の感じと日本語の感じが異なったのだと思います。
アンソロジーということで、色々な作家の作品が入っています。そのため、良いと思った作品とそうではない作品とかなり大きな差が出た気がします。この本を読んで1ヶ月ほど経つのですが、上記に挙げた2作品以外、あまりストーリーを覚えていません。これがアンソロジーという分野なのでしょうか。
Xの悲劇(by エラリー・クイーン:1932) [読書’15]
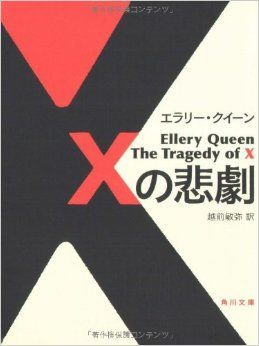
松本清張の「黒い手帖」にエラリー・クイーンという読んだことのない作家の名前が登場していました。松本清張が、まずまず評価していたので、読んでみることにしました。たくさん作品があるので迷ってしまいましたが、「容疑者Xの献身」にタイトルが似ているから、と単純な理由で、この「Xの悲劇」と決めました。
本当は原書で読んでみたかったです。そこで、最初は英語版の購入申し込みを試みました。が、結果的に難しいということが今回調べて分かりました。私が利用する図書館は、本の購入申し込みが出来るので、英語版を申し込んでみようとしました。図書館が購入するので、その申し込みが受理されないことももちろんありますが、外国語の本も結構購入してくれています。そして、今回も同様に申し込んでみることにしました。新規購入申し込みの際、出版社や出版年、値段(定価)など詳細情報を申込用紙に記入していかなくてはなりません。私はいつも、こういった詳細情報を大手ネット通販サイトで見ています。 しかし、このサイトで「Xの悲劇」(英語)の値段が表示されません。絶版になっているため、オークションでしか手に入れることが出来ないようで、その値段はなんと7000円。そして色々調べてみると、日本でも古本屋でしか手に入れることが出来ないようです!神田にある外国語の古本屋は「エラリー・クイーンの本多数取り置き」という宣伝文句を掲げていました。
結局原書を取り寄せることは出来ず、日本語で読みました。主人公の名探偵が、元シェイクスピア劇の舞台俳優という役設定だったので、彼のしゃべり方は芝居の台詞のようでした。実際有名なシェイクスピア劇からの引用も多く、原書で読むと日本語では分からない英語のリズム感があるのだと思います。
本格的な「推理小説」(トリックが重要視)と聞いていたので、私も読みながら推理してみました。しかし、色々な殺人事件が起こるのですが、どれもお手上げでした。解決編部分を読むと、はっきりとそのヒントとなる文章も思い出せるのですが、解決編前では全く分かりませんでした。
主人公は探偵ではなく、本職は舞台俳優。捜査に関しては素人とも言える人に、警察が推理を聞きに行くというのは不思議でした。物理学者(大学の准教授)に警察がトリックのアドバイスを求める、というストーリーは何となく理解出来るのですが、俳優にアドバイスを求めるのか、と読んでいて最初は思ってしまいました。しかし、例えば医者を演じている時、「この人は医者にしか見えない」と観客に思わせるためには、医者という人間の観察が欠かせません。その職業/人柄の特徴をしっかりつかんで、自分の体で表現するということが出来なければ、その人にもなりきれないと思います。人間観察というツールを使って、捜査ができる俳優と考えれば、この俳優=名探偵ということも納得出来ました。
The Remains of the Day (by Kazuo Ishiguro : 1989) [読書’15]
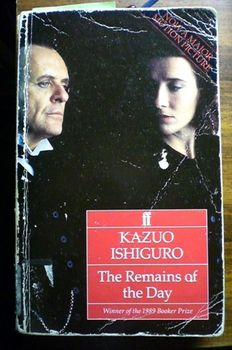
名前は日本っぽいですが、イギリス作家です。読んだイギリス作家の数は少ないですが、私の好きなイギリス人作家かもしれません。彼の作品の特徴は、「記憶」です。現代だったり、戦後だったり、日本だったり、イギリスだったり、舞台や時代背景は作品ごとに異なります。しかし、必ず「記憶」が話の中心になっています。記憶のぼやけた感じが、少しイギリスのどんよりした天気を私には思い出させます。
イギリスの歴史ある館で、執事を務める男性の話です。貴族、執事、という、完全なイギリスのイメージが、読者を裏切ることなく描かれています。「dignity」、日本語にどう訳すか難しいところですが、「品格」や「尊厳」という意味が辞書には出ています。仕事の品格、というのが、この本のテーマの一つです。仕事や自分のやっている事の意味を考えると、これはとても重要なテーマな気がします。特に、自分の仕事や人生をよく考えていた時期に読んだので、主人公である執事の話にはグッときました。読んでいても、「私にとって品格とは?」など考えてしまいました。
そして、この本でよく登場する言葉が「gentleman」。執事を表すのにぴったりの言葉ではないでしょうか。同時に、定義が難しい言葉です。私がgentlemanだなあと思える人を何度か見かけたことがありますが、共通項は見つからず、まだ定義出来ていません。
また、第一次大戦後のイギリスから見たヨーロッパも描かれていて、とても面白かったです。当時(そして今も)、イギリス人からすると、フランス人は変わった人だったようです。特質というか、理解出来ない人達、という感じだったようです。私達からすると、「ヨーロッパ」と一括りにしてしまいますが、ドーバー海峡(フランス語では「カレ海峡」)は大きな隔たりなのでしょう。
少し時間がかかりましたが、飽きることなく読み終えることができました。この本を読むまで、個人的には、彼の作品では「Never let me go(私を離さないで)」が好きでした。私が「Kazuo Ishiguroが好きだ」という話をすると、皆「The Remains of the Day(日の名残り)が良い!」と口を揃えて言います。ずっと気になっていて、読みたいと思っていました。そして、同じような話をイギリスの友人にしたところ、彼女がその本を貸してくれました。ちなみに、この会話は数年前のこと。彼女は、以前我が家にホームステイしていたイギリス人。私がロンドンへ遊びに行った時、8年ぶりの再会を果たし、その時に彼女が「次会うときまで貸してあげる」と言ってくれたのです。その時から、早3年が経ってしまいました。ようやく読み終えたので、早く返さなくてはならないのですが、いつになることやら。
Novel 11, Book 18(by ダーグ・ソールスター:1992) [読書’15]
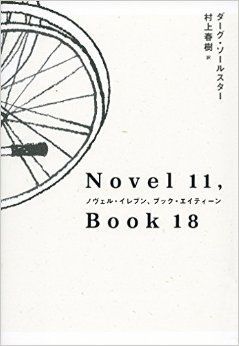
ノルウェイの作家の作品です。書かれたのは20年近く前、今年翻訳されたものです。ノルウェイの作家は誰一人知らないのですが、先月この本の翻訳が出たので読んでみることにしました。その翻訳をしたのが、村上春樹です。彼が期間限定でやっているホームページにて、この本が宣伝されていたのでした。しばらく彼の(翻訳)作品を読んでいないので、久しぶりに読んでみるか、と早速図書館で注文してもらいました。
4月に発売されたばかりだったので、まだ図書館も購入していなかったようです。そのため、購入してすぐ私の手元にやってきました。誰もまだ読んでいない本を開くというのはとても気持ちいいものです。新しい本を開けた時の「プチッ」という音が私は大好きです。足跡のない新雪に踏み込む感じに少し似ている感じがします。
読んだ感想は、「何じゃこれ?!」というものでした。今までに読んだことがないスタイルで、どう表現したら良いか分からないという感じでした(映画「マルコヴィッチの穴」を見た時も同じような感覚を抱きました)。どんなジャンルの本か、と聞かれても、どのように答えたらよいか分かりません。知りたい人は、自分で読んでください、と言うしかない気がします。
この作品、訳者あとがきでも書いてあったのですが、とにかく文章が入り組んでいます。「ときほぐす」と訳者も表現していましたが、読んでいてもそういう感じでした。200ページちょっとの作品でしたが、読み終わるのに1週間以上かかりました。この作品、ノルウェイ語から英語に訳されたものを使って日本語に訳されているようです(いわゆる重訳)。英語で読んでみたい気もしますが、理解出来るかちょっと不安な部分もあります。
ただ、作品の雰囲気としては私好みでした。ここ数年映画を見ていて感じることなのですが、私は結構劇タイプの作品が好きです。劇が元になった作品や、劇のように場所の変化が無く、台詞が延々と続く作品、劇の中で劇を演じるというのも好きなジャンルです。
この小説も少し劇っぽいところがあるので、読んでいて面白かったです。語り手の主人公が一応居るのですが、同時に劇の演出家として「自分自身の役」も演出しているので、一人称である自分が三人称のように客観的になっている部分もありました。そういう視点の変化も読んでいて面白かったです。
この作品が面白かったので、同じくホームページで宣伝されていた村上春樹自身の作品も読んでしまいました。The New Yorkerというおしゃれな雑誌(エッセー、レポート、批評、何でも載っている雑誌)に彼の短編作品の英語版が先日載ったということでした。KINO(木野)という作品です。アルファベットの「KINO」では漢字が思い浮かばず(札幌にある映画館の名前「シアター・キノ」しか思い浮かばなかった)、どんな作品なのか興味が沸きました。ただ、彼の作品タイトルはどれも内容が想像出来るものではないので、漢字が分かったとしても、変わらない気がしますが。彼の長編は英語でチャレンジしたことがあるのですが、途中で挫折しました。しかし、今回は短編だから大丈夫だろうと言い聞かせて読んでみました。すると自分でも驚いてしまったのですが、サラッと読めました。A4の紙26ページぐらい(画面で読む自信がなかったので、印刷)、びっくりするほど早く読めました。一番の理由は、この主人公に共感出来たからだと思います。読み終わって「分かるなあ、この気持ち」とすっきりしました。彼の作品をもっと読んでみたい、と初めて思いました。
というわけで、村上春樹関連2作品を堪能した週となりました。



